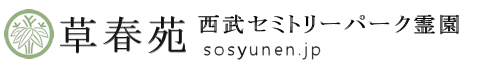- 草春苑トップページ>
- 飯能のエコツーリズム>
- エコツーリズムイベント案内
このページは飯能市役所提供の資料を基に制作しました。
エコツアーのご案内ページはこちらから
エコツーリズムのまち 飯能
 飯能市を訪れる方に、地域の自然や歴史、生活文化をご案内し、体験し、楽しんでいただくこと。
飯能市を訪れる方に、地域の自然や歴史、生活文化をご案内し、体験し、楽しんでいただくこと。
これが飯能市のエコツーリズムです。
訪れる方に満足してもらうことのほかにも大切なことがあります。
それは、地域の魅力の源である自然を守り、文化を継承していくこと。
そして、そこに暮らす私たちが地域の魅力を再発見し、地域が元気になっていくことです。
エコツーリズムとは
自然や歴史、文化を体験しながら楽しく学び、それらの保全にも責任を持つ観光のあり方です。エコツアーとは、エコツーリズムの考え方を実践するツアーで、飯能では「人とのふれあい」と「体験」を重視し、「地域の人が、地域の言葉で、地域を案内するエコツアー」がおこなわれています。
大切にしていること
- 自然の保全と文化の継承に役立つこと
- 地域の自然や文化が題材になっていること
- 住民が地域の良さを再発見すること
- 旅行者や住民の考え方や行動が自然や環境と調和したものになること
飯能市エコツーリズムの取り組み
 飯能市は、東京都心から約1時間、埼玉県の南西部にあるまちです。
飯能市は、東京都心から約1時間、埼玉県の南西部にあるまちです。
山地・丘陵地・台地と地形の変化に富んでいて、まちの4分の3は森林が広がり、源流から中流までの様々な川の姿を見ることができます。
こうした身近にある自然との共生によって、古くから人々のくらしや文化・歴史、産業が育まれてきました。
これらの身近な自然や地域の生活文化を活かしながら次の世代に残していくために、飯能市では2004年の環境省エコツーリズム推進モデル事業に応募しました。
同モデル地区に指定ことを機に、市とエコツーリズム推進協議会が中心となって、エコツーリズムに取り組んできました。2008年には、環境省が主催する第4回全国エコツーリズム大賞の『大賞』を受賞、2009年には全国で初となるエコツーリズム推進全体構想の認定を受けました(その後、改訂を行い、2015年に再認定)。
一人でも多くの飯能のファンを増やすために、引き続き市民と行政が一体となって取り組みを続けていきます。
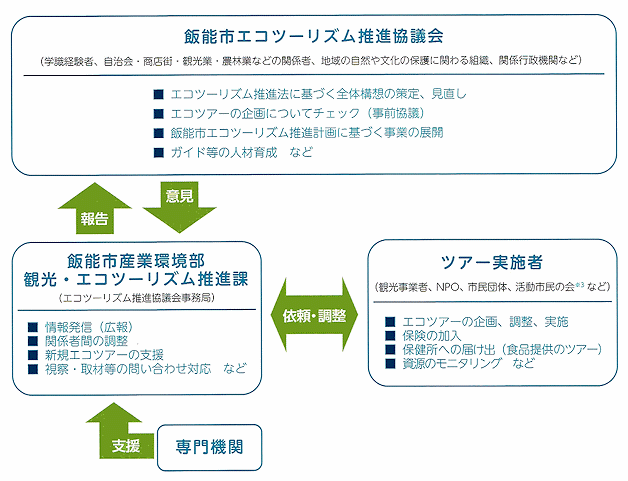
- エコツーリズム推進協議会とは
- エコツーリズム推進法に基づき設置したエコツーリズムに関わる地域の多様な主体の話し合いの場
- エコツーリズム推進全体構想とは
- 自分たちの地域でどのようにエコツーリズムに取り組むかをまとめた構想
- 活動市民の会とは
- エコツーリズムの活動を通じて、飯能の自然、歴史・文化を守り、楽しもうという市民のグループ
飯能市でエコツアーを実施するまでの流れ
エコツーリズムで目指す地域の姿と三つの基本方針
自然・文化・人のつながりによって発展する活力ある地域
飯能市では、エコツーリズムの推進によって目指す地域の姿と、その実現のための基本方針を定めています。
- 基本方針1
- すべての地域と住民の参加により、地元への誇りと愛着を育みます。
- 基本方針2
- 訪れるたびに新たな発見や変化のある楽しく満足できるエコツアーを提供します。
- 基本方針3
- 飯能市の自然を保全・再生し、文化を継承して将来へ伝えます。
飯能市エコツーリズム10の推進ポイント
飯能市を特徴づけている多様な自然やそこで育まれた文化、都心から約1時間という利便性などを活かすために、エコツアーを企画・実施する際のポイントを設定しています。

ポイント1
住民が誇りとするふるさとの風景の保全・再生に活かす

ポイント2
自然を守り育む森づくりにつなげる
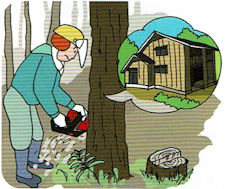
ポイント3
飯能市の森林文化を新たな地域の発展に活かす

ポイント4
源流から中流までの親しみ深い川の自然と文化を活かす
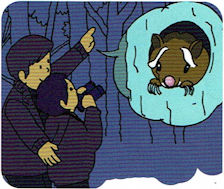
ポイント5
さまざまな野生生物の魅力や人との関わりを題材とする

ポイント6
身近な自然を保全・再生し、自然豊かなまちづくりに役立てる

ポイント7
地域の生活文化や年中行事などの伝統を活かす

ポイント8
長い年月をかけて培われた伝統的な技術を新たな時代に活かす

ポイント9
地域住民の全員参加により、一人ひとりの個性を活かす

ポイント10
繰り返し訪れたり宿泊したりすることで地域の魅力を堪能できるエコツアーを用意し、飯能のファンを増やす
飯能市エコツーリズムのルール
ガイドが守るルール(要約版)
野生の動植物を守るために
- 原則として野生の生きものを捕まえたり、採ったりしない。
- 観察した生きものは元の場所に戻す。
- 野草や山菜の採取は必要最小限にとどめ、根絶やしにしない。また、事前に土地所有者の了解を得る。
- 里山に生育する花の美しい植物や、希少な動植物を守るために配慮する。
- 野生の生きものに影響を与えないように観察方法や観察場所を工夫する。
- 野生の生きものに餌を与えない。
- 野生の生きものに悪影響が出ないようにツアー参加人数を設定する。
- 自然の管理は、専門家の助言を得て行う。
- 他地域の生きものや外来生物の持ち込みや増殖は行わない。
- 河原での直火の使用や、調理した油の川への流出、河川敷への車の乗り入れなどは行わない。
- 壊れやすい自然の場所への立ち入りは注意する。

文化を継承するために
- エコツアーでの活用が伝統文化を変えないようにする。
- 資料は丁寧に取り扱う。
- 資料の借用はできるだけ避け、コピーを取ったり、写真を撮影するときは所蔵者の了解を得る。

環境を守るために
- 西川材を利用した木製品や、地元で栽培された野菜など、地元産品の利用を進める。
- 環境への負担が少ない製品の使用を進める。
- ごみの排出を極力抑える。
- 公共交通機関の利用を考慮したスケジュールとし、参加者に公共交通機関の利用を呼びかける。
- 参加者にエコツーリズムの目的や考え方、ルールについての理解を促す。
住民の生活環境を守るために
- 住宅の敷地や農地などに立ち入る場合は、事前に土地所有者の承諾を得る。
- エコツアーの実施日時や目的について、事前に地域住民に説明し、エコツアーへの理解を得る。

参加者の安全を守るために
- 保険に加入し、事前に補償内容を参加者に説明する。
- 緊急時の連絡先や対応などを明確にしておく。
- 下見をして危険を把握し、対策を考える。
- ツアー開始時やツアー中に、起こりうる危険を参加者に説明し、注意を促す。
より良いエコツアーとするために
- 飯能市エコツーリズムの基本方針などに沿ったエコルアーを行う。
- 定員は、参加者全員が安全に楽しめる人数設定とする。
- 準備を十分に行い、募集の際に示した内容を守る。
- ツアー開始時にスケジュールやツアーの目的について説明する。
- 持てなしの心と気遣いを持ってツアーを行う。
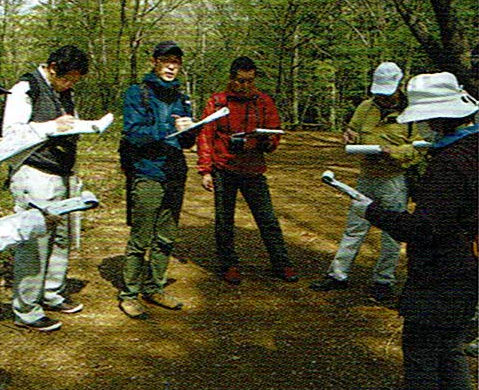
参加者が守るルール(要約版)
- ツアー中はガイドの注意を守る。
- 樹木や地層、岩などに傷をつけたり、落書きをしたり、持ち去ったりしないようにする。
- 史跡や建物などに傷をつけたり、落書きをしたりしないようにする。
- 飯能に伝わる伝統文化を尊重する。
- ごみは捨てずに持ち帰る。
- 公共交通機関の利用に努める。
- ツアーの内容に適した服装や持ち物で参加する。
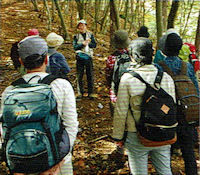
エコツーリズムを通じたまちづくり
飯能ファンの増加
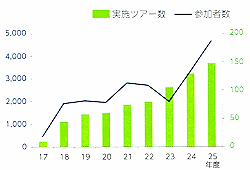 「あ!こんにちは」「またお会いしましたね」-飯能のエコツアーでは、こんな会話をよく聞きます。年間150のツアーが行われ、4000人以上の方にご参加いただく中で、飯能のファンになり、1年に何度も訪れてくださる方もいらっしゃいます。エコツーリズムは飯能の観光事業の中で大きな柱に育っています。
「あ!こんにちは」「またお会いしましたね」-飯能のエコツアーでは、こんな会話をよく聞きます。年間150のツアーが行われ、4000人以上の方にご参加いただく中で、飯能のファンになり、1年に何度も訪れてくださる方もいらっしゃいます。エコツーリズムは飯能の観光事業の中で大きな柱に育っています。
地域の魅力の再発見
 エコツアーの企画のために地域の人材や資源の発掘が行われ、住民が地域の良さを再発見することにつながっています。その結果、地域への誇りや愛着が生まれ、地域が元気になっています。
エコツアーの企画のために地域の人材や資源の発掘が行われ、住民が地域の良さを再発見することにつながっています。その結果、地域への誇りや愛着が生まれ、地域が元気になっています。
里山の保全、環境教育の推進
ボランティア活動ではなくエコツアーに参加していただく中で、ブラックバスの駆除やビオトープづくり、竹の伐採などの里山の保全活動を楽しみ、環境保全意識の向上にも結びついています。遠足で訪れる小学生をエコツアーガイドが案内するなど、環境教育にも力を入れています。
地域経済への貢献
 エコツアーの中で地元の食材を活用したり、市内のお店を利用したりして、地域経済へ貢献できるよう工夫しています。また、お客様にはできるだけ公共交通機関を利用していただくようお願いしており、利用機会の増加につながっています。
エコツアーの中で地元の食材を活用したり、市内のお店を利用したりして、地域経済へ貢献できるよう工夫しています。また、お客様にはできるだけ公共交通機関を利用していただくようお願いしており、利用機会の増加につながっています。
まちのPR
 「エコツーリズムのまち飯能」として、市街・海外から大勢の方がエコツアーに参加したり、視察で来ていただいたりするようになっています。自治体や大学の研究者などによる視察は年に20回以上あり、その他にもイベントでの出展や講演、新聞やラジオなどのメディア掲載を通じて、まちのPRに役立っています。
「エコツーリズムのまち飯能」として、市街・海外から大勢の方がエコツアーに参加したり、視察で来ていただいたりするようになっています。自治体や大学の研究者などによる視察は年に20回以上あり、その他にもイベントでの出展や講演、新聞やラジオなどのメディア掲載を通じて、まちのPRに役立っています。